こんにちは、さわです!
新人看護師の指導の中で、よく耳にする言葉があります。
それは——
「わからないことがわからないんです」
何をどのように勉強して、
どこまでわかっていればいいのか?
看護師として働く中でそう思ったことはないですか?
私も新人の頃は悩んでいたし、
指導する立場になると改めて
正直何をどこまで教えればいいのかわからなくて、
困っています💦
でも、わからないながらも、どうすればいいのか考えてみて、
一つの答えがわかったような気がしたんです。
『わからないことが、わからない』
この言葉はきっと
誰もが通る“成長の通過点”。
今回は、そんな「わからないことがわからない」を打破するための指導のヒント、
新人看護師にしてほしいことを
私自身の体験をもとにお話しします。
✅なぜ「わからないことがわからない」のか?

今まで学校では、テストを通じて
◯と✕がついて
「自分がわかっていないところ」が明確になりますよね。
でも、医療の臨床現場にはその「テスト」がありません。
だから、新人が「何を知らないのか」に自分で気づけないのは、むしろ自然なこと。
そして、教える側も
✔「何をどこまで説明すればいいか」
✔どこまでが自己学習?
✔どこまでが教えるべきところ?
明確になっていないから
指導が難しくなるのではないかなと思いました
✅指導カギは「わかっていることを見える化」すること
私が新人だった頃、
自分なりに工夫していたのが
「わかっていることをノートに書き出す」ことでした。
たとえば:
- 自分が受け持っている疾患
- 必要な観察項目
- どんなアセスメントが必要か
- なぜそれをするのか(根拠)
こうして“自分の理解”をアウトプットすると、
「あれ?ここは自信ないな」「これは調べた方がいいかも」と、
不足が自然と浮き彫りになります。
そして、そのノートを先輩に見せると、
「ここはOKだけど、こっちはこう考えるといいよ」 と、具体的なフィードバックがもらえるんです。
これは別にノートでなくても、
自分で口頭でアウトプットできればそれでいいと思います。
聞きたいことを聞きだす力が”質問力”でしたね。

✅教える側も“土台”がほしい
何も提示されない状態で「何か教えてください」と言われると、
正直困ってしまいます。
たとえば、
「ピーマンって何ですか?」
と言われても答えに困りますが、
「ピーマンはなぜ緑色はなんですか?クロロフィルという色素を多く含んでいるからだと文献を調べると出てきました。他に知識として知っておくといいことはないですか?」
と聞かれると、少し調べれば具体的に答えられます。
これは、新人の質問に「土台(=背景や理解度)」や「焦点」があるかどうかの違い。
“どこまでわかっているか””何を聞きたいのか”がわかれば、
的確なアドバイスがしやすくなります。
✅「仕事ができる人」に近づくための思考訓練
アウトプット → フィードバック → 改善
この繰り返しが、「できる人の思考法」を育ててくれます。
指導者としては、
「今、わかっていることを教えてください」
というスタンスで新人に接することで、
その人の“伸びしろ”が見えてくるのではないかな?と思います!
✅まとめ:「最初の一歩」は、アウトプットから

新人が「わからないことがわからない」のは自然なこと。
だからこそ、
“わかっていること”を
まず新人看護師さんへ
アウトプットしてもらうことが、指導の出発点ではないのかな?
と思いました!
教える側がすべてを与えるのではなく、
新人の「理解の輪郭」をもとに、不足を補っていく。
このプロセスこそが、教育の近道なのではないかな?と思います。
現場で悩んでいる新人さんも、指導に迷う先輩方も、
ぜひ「アウトプット→フィードバック」のサイクル
なにかの参考になれば嬉しいです!
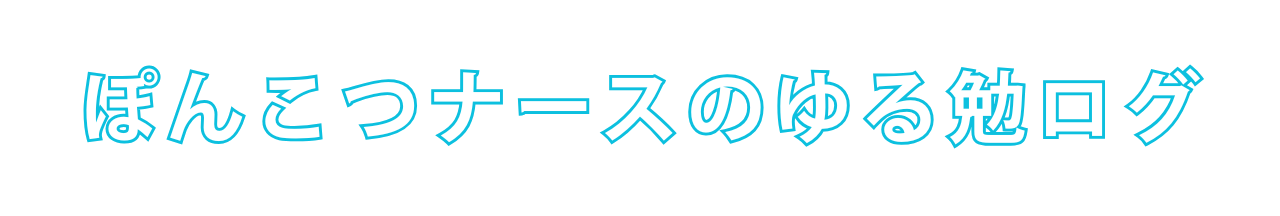
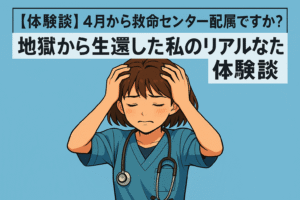
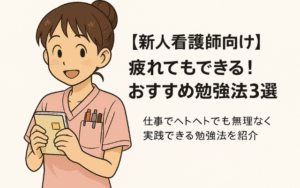


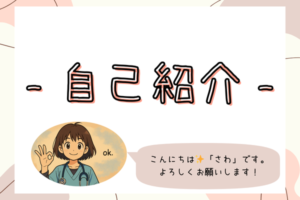
コメント