こんにちは。
看護師×新人教育奮闘記の「さわ」です!
4月を終えて、5月になりました。
現在の職場は教育が少しやばいです💦
今までの看護業界は、”恐怖教育”耐えることができる、
自分で学習可能な人材は自動的に残るシステム
だったかなぁと思うのです。
しかし、少子化、看護師不足、パワハラ問題により
”恐怖”で教育することができなくなり、
「自分で学習したくない新人」が増えています。
その結果、
✔状態不良の患者を放置してしまったり
✔アセスメントできない看護師が増えている
現在の職場です。
今回の記事では、
”できる人材を育てるプログラム”構築のために
必要だと考えた私のSTEP1について
思考を整理するために書きます。
5月、ふと立ち止まって考えた「このままでいいのかな?」

4月が終わり、少し落ち着いた5月。
この職場にきて、1年目の私。
私はこのゴールデンウィークの間、
ずっと「新人教育をどうにかしたい」と考えていました。
というのも、
毎年同じような教育の悩みを感じながら、
どこか「仕方ないよね」と流している職場なのです。
でも今年は違います。
なんとかしたいのです。
去年働く中で病棟の課題をたくさん発見しました。
私のこの1年間の目標は
本当に意味のある教育をしたい。
これにつきます。
このGW、悩んで、考えて、書き出して…。
ようやく一つ、「最初にやるべきこと」が見えてきました。
教育体制、整ってるようで整ってない
今の現場には、こんな課題があります。
- 誰が新人を教えるのか、決まっていない
- 新人は「誰に質問したらいいの?」と困っている
- 教える人によって言うことがバラバラ
- 気づいた人・できる人が教えてしまい、仕事量の偏りが生まれている
つまり、「教育する仕組み」がないまま、
誰かの善意でなんとか回している状態なんです。
前述の通り今までの教育方式が機能しておらず、
少子化、看護師不足、パワハラ問題の影響で
人材が不足し、教育がゆるくなった結果、
自主学習しない人が増え、なんとなく看護になっている現状があります。
そのため、よくわからないまま育っている3〜4年目が多く、
「適当でいいよ!」なんて教え方をする3年目もいます💦
これは、教える側にも、新人にも、
不安を抱えたまま仕事をすることになり
いつか取り返しのつかない過ちにつながるかもしれません。
このままでは、
✔できる人材は育たず、
✔やりがいも感じず
✔できる人は外に出ていく
負のスパイラルにハマってしまいます。
今こそできる人材を育てるプログラムの構築が必要なんです。
私が考えた“ステップ1”は「教育担当者の明確化」

「できる人材育てるプログラム」構築するために
提案させてください。
それは。まずは誰が新人を担当するのかを決めること。
これが、私にとっての「ステップ1」です。
なぜこれが大事かというと、
- 新人が安心して相談できる
- 教える側も「責任を持って向き合おう」と思える
- 教育のゴールを共有しやすくなる
というメリットがあるからです。
どうやって科長に伝える?
この提案を実現するには、科長に相談する必要があります。
そこで私は、まず現場の「バラバラさ」を伝えるつもりです。
Aさんはこう言う、Bさんは違うことを言う、Cさんもまた違う…。
結局、新人は「何が正解か分からない」と悩んでいます。
このような現状を共有した上で、
- 教える人を決める
- 教える内容のゴールを共通化する
- マニュアルや指導方針を明文化する
といった改善策を提案したいと思っています。
人は“成長できる場”に喜びを感じる

私は、人は本来「成長したい」と思っている生き物だと思っています。
教育が整っていれば、
- 自分で考えて行動できるようになる
- 成長の実感が得られる
- 「ここで働き続けたい」と思える職場になる
つまり、職場の満足度・定着率にもつながるんです。
教育制度を整えることは、新人のためだけじゃなく、
現場全体の未来への投資だと思っています。
次は「仕事ができる人」を育てるための準備を
今回の提案がうまく伝えられたら、次に考えているのは…
教育担当者に「どんな人材を育てるか」というゴールを共有すること。
「仕事ができる新人」とは?
「そのために、どんな行動・思考が必要か?」
それを分かりやすく伝えるプレゼンも準備していく予定です。
まとめ
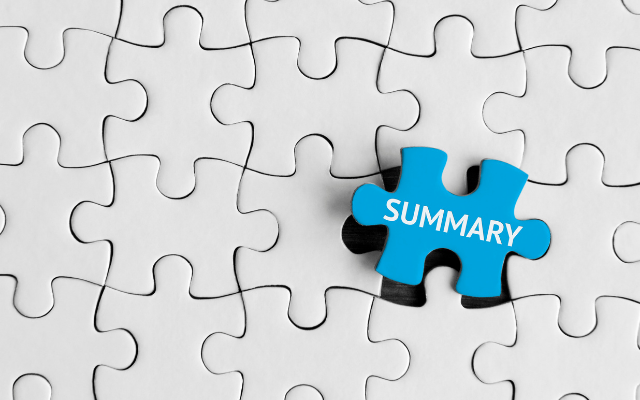
私が病院の教育を改革するための
STEP1は「まず、誰が教育担当かを決めること」
メリットは
- 新人が安心して相談できる
- 教える側も「責任を持って向き合おう」
- 教育のゴールを共有しやすい
私は”教育”を整えることは組織の基盤になると思います。
みんなが同じような目標をもって
それぞれの強みを活かして仕事をしたほうが
楽しいと思います。
仕事が楽しいと思う人が今の職場で少しでも増えればいいなと思います。
次回はその結果と、その後の方針についてお伝えします!
応援よろしくお願いします!
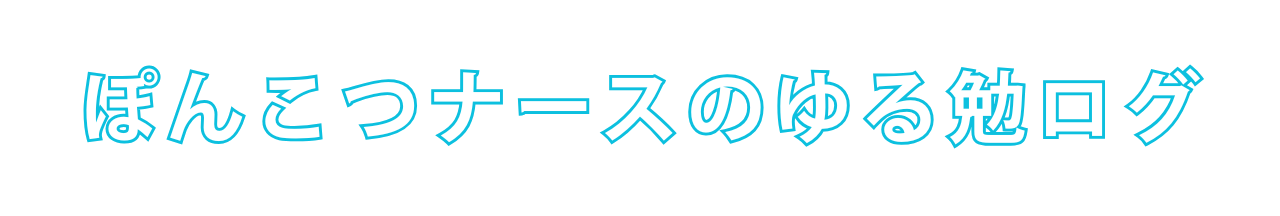
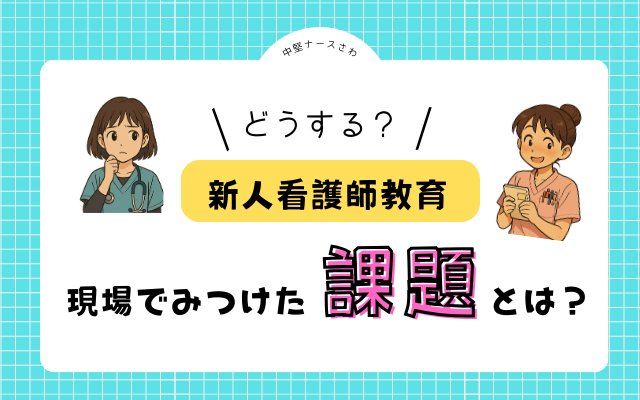

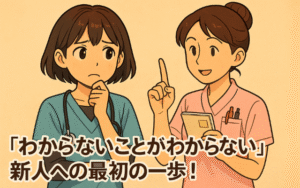
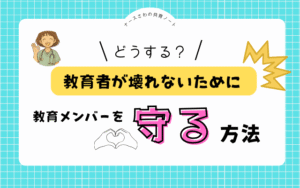
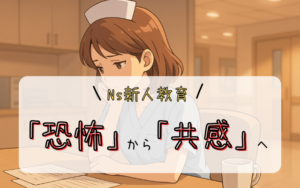
コメント