はじめに
こんにちは!さわです✨️
今日も新人教育を進めていきます!
現在までの流れ
①教育メンバーを決定した
②特別アドバイザー制度を取り入れた。
今回の記事はその続きです。
③教育者に”仕事ができる新人を育てる方法”を伝える方法になります。
というのも、
今や医療現場においても、
ただ単に指示を出すだけの教育では不十分な時代となりました。
「1を聞いて10を知る」スタイルでは今の子は育ちません。
かといって、
「10ある事柄をそのまま10伝えても」
自分で考える力をが育たず、
指示待ち人間が出来上がります。
現代の新人教育に必要なのは、単に知識を教えるのではなく、
主体的に考え、行動できる「仕事ができる人材」を育成することです。
”仕事ができる”って曖昧で、抽象的な表現ですよね。
でも、私達が育てたい人材は、
”仕事ができる人”だと思うんです。
今回のターゲットは
✅️自分で進んで学習できる人
✅️患者さん思いで、誰かのために頑張れる人
に向けていません。
できる人は放っておいても成長します。
ターゲットは、
【やる気がない、勉強の仕方がわからない人】です。
”仕事ができる”マインドの人を育てるプログラム構築を目指しています。
この記事では、
働きやすい職場づくりやチーム医療の良循環を目指すために、
教育の最終目標やその具体策、
そして実際に現場で活用できる方法について掘り下げます。
この記事が向いている人
✅️新人教育に悩む管理職の人
✅️新人教育に悩む中堅看護師
✅️新人看護師
こんな立場の人には参考になるのではないかなと思います!
では行きましょう!
1. 教育の最終ゴールって何だろう?
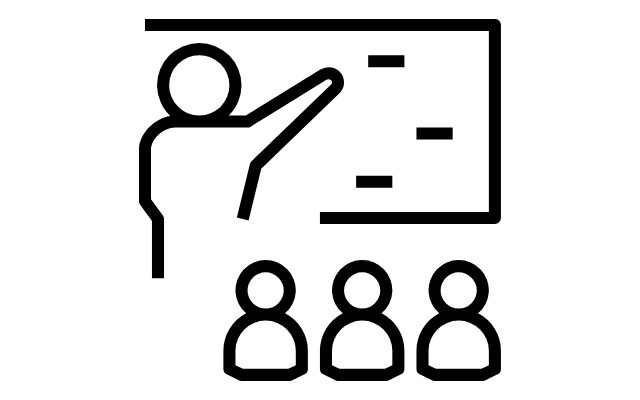
教育の目的の再確認
私たちが教育に求める最終的なゴールは、
単なる知識の伝達ではなく、「仕事ができる人材を育てること」にあります。
そして、医療現場では、誰もが自分の判断で的確に行動できる力が必要です。
イメージしてみてください。
去年の出来事でこんなことがありました。
私が夜勤の勤務で来たら、
患者さんが血圧60/42mmHg、
顔面蒼白、意識レベル低下がありました。
その方は朝から高熱があって、
ぐったりしている様子だったようです。
新人さんは、ただ朝に一回血圧を測る。
ことだけを実施し、
その後の異常のあるなしが判断できていないため、
対応ができていなかったのです。
言うまでもなく、
看護師はただ血圧を測るだけが仕事ではありません。
その先の今測定した、
血圧が異常あるのか、ないのかの判断が最も大事なのです。
医療者であれば、血圧60になる前に、
今朝から40度の発熱があるのであれば、
モニターをつけて、血圧を定期的に図り、
ショックの兆候はないのかどうか予測して動く必要があります。
このような判断、行動までは難しいかもしれませんが、
でも、”自分の対応がこれで正しいのか”先輩に聞く
【わからない、不安だと思う】▷【相談をする】
という行動を自分で考えて発信してもらう必要があるんです。
指示待ち人間ではだめなんです。
なぜなら、
✅️同じ勤務帯で働いている先輩の方が重症度が高い
✅️受け持ちの人数が多かったり
✅️その他電話対応なども多く業務を引き受けている
上記の理由のため、
新人さんの受け持ちの人まで見に行けないのです。
(※12月でフォローの期間は終わっていた)
その後しっかりと指導しましたが、
何かがあってからでは遅いのです。
なぜなら、医療現場は”命に関わる仕事”だからです。
「ああ、やっぱり看護師怖い、無理かも、、、」
って思うかもしれません。
でも大丈夫。
「これがわからない」それが発信できれば大丈夫。
その後は、フォローします。
だから、先輩がするべきことは、
✅️「話しかけやすい雰囲気作り」
✅️「異常のあるなしの判断の基準」
を教えていくことだと思うんです。
「仕事ができる」この曖昧な言葉を定義する
看護師において、
指示待ち人間は絶対にだめな理由はお分かり頂けたと思います。
要は、看護師は自ら考えて行動ができる
「仕事ができる」状態を目指さなくていけません。
では、
✅️「仕事ができる」状態とはどんな状態なのか?
✅️どうやって育成すればいいのか?
✅️どのようなスキルやマインドが必要なのか?
明確に定義し、現場で活かせる形に落とし込むことが、教育改革の第一歩となります。
2. “仕事ができる人”とはどんな人か?
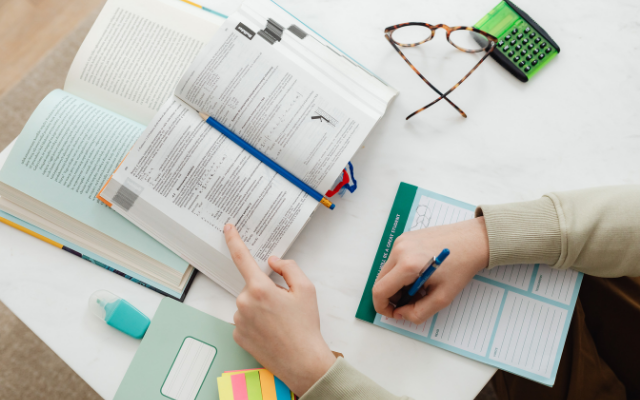
仕事ができるを定義する
「仕事ができる人」の定義について、ある書籍から多くの示唆を得ました。
その書籍で紹介されていた。仕事ができる人の定義は以下になります。
- 具体的な定義の3要素
- 相手の期待を超える力
常に先輩や上司が想定する以上の成果を出し、信頼を得る。 - 言語化と共有の力
数字では測れない業務に対して、自らの期待値を明確にし、他者と共有できる。 - 具体的な行動への落とし込み
曖昧な表現ではなく、具体的な行動で結果に結びつける力が求められる。
- 相手の期待を超える力
まだまだ、抽象的でイメージが湧きませんね。
3. 思考力のある人を育てるマインドセット
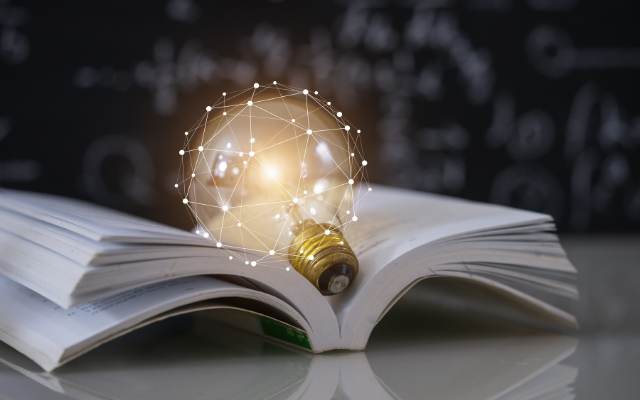
「わかったふり」しない勇気
自分が理解していると安心するのではなく、
✅️自分の理解はこれであっているのか?
✅️「知らない」、「わからない」に遭遇した時に
疑問点や不明点を積極的に洗い出す姿勢が、成長への大きな一歩です。
言葉の定義と認識のすり合わせ
コミュニケーションの基本は、双方の認識を一致させること。
例えば、タスクの依頼時には「はい、わかりました」だけでなく、
確認の質問を交えることで、双方の理解度が深まります。
アウトプットによる自己評価
新人が自分の考えを言語化し、
先輩や上司とすり合わせることで、
自身の位置や課題を客観的に捉えられるようになります。
このマインドセットが仕事をできる人のマインドなので、
このマインドに持っていくことが教育者の役目です!
次の項目で具体的にイメージしてみましょう!
【退院調整のケース】
主任NS:Aさん退院調整しておいて。
指示待ち人間:はい、わかりました
仕事ができる人:
「Aさんの単位調整についてですが、施設での調整で間違いないでしょうか?
その場合、私に求められている行動は何か、MSWに一度相談すべきか確認させてください」
という感じです。
後者の行動をすべての新人に目指してほしいのです。
二人の違いは
✅️自分の認識があっているかを確認しているかどうか
✅️自分の認識をアウトプットしている点
が違います。
同じ指示に対しても、
確認の有無で成果の差がどんどん生まれます。
この時大事なのが、
✅️新人さんの言葉で、自分の現時点での理解度を言語化することです
このアウトプットが大事であることを
強調させてください。
なぜか?
先輩の思考(仕事ができる人)と
自分の思考のギャップを認識、かつ明確にするためです。
自分の思考を定義することで、
やっと、自分の思考の足りていないことがわかるんです。
この本の中では、こんな事例で紹介されていました。
先輩:この書類多めに印刷しておいて
新人:はい、わかりました。
先輩:おい、何部印刷しようと思った?
新人:え、10部です。
先輩:違う、20部だ。なんで確認しなかった?
このやり取りです。
新人視点ではもしかしたら、
「それなら最初から20部印刷して」って言えばいいじゃんと思うかもしれません。
違うんです。
一見遠回りに見える。
このやり取りが教育においてものすごく大事なんです。
上記のやり取りは
新人さん側から、「認識のすり合わせをする」ように意図しています。
✅️自分の理解度を言語化すること
✅️自分の理解度を確認すること
が仕事ができる人の定義でしたね!
その人材を育てるために、あえて、そうしているんです。
そして、この行動こそ、教育する側がするべき行動なんです。
4. 教育者が意識したい5つの「ない」

もうね、文章長すぎて、疲れた人もいると思います。
もう少しお付き合いください。笑
教育者がするべき行動がなんとくわかったところで、
現代の教育現場で、新人がより成長しやすい環境を作るために、
絶対に避けるべき言動を以下にまとめます。
わからない言葉をスルーしない
知らないことはそのままにせず、必ず質問して理解を深める。
答えを当てにいかない
自らの考えを大切にし、安易に答えを求めるのではなくプロセスを重視する。
動機に依存しない
単なる「やる気」だけに頼らず、具体的な行動と成果を意識する。
陰口を言う人に近づかない
建設的な意見交換の場を作り、ネガティブな情報に左右されない。
笑顔を絶やさない
どんな状況でもポジティブな姿勢を保ち、チーム全体に良い影響を与える。
これらの行動を新人に身につけてもらえるように意識しましょう。
8. 「質問の仕方」も教育の一環
- 質問は範囲を絞って具体的に
例:「肺炎について教えて」ではなく、「肺炎の治療における抗生剤選択の基準は何か」といった、具体的な質問が望ましい。 - 教える側も困る現実
質問が漠然としていると、教える側は本来の業務が滞る可能性もあるため、まずは自分で調べ、どの部分が不明確なのかを整理してから質問する習慣が大切です。 - 時間を有効に使う意識の醸成
質問をする際は、相手の時間を奪う行為であることを意識し、事前準備を徹底することが、新人教育の質を高める鍵となります。
具体的には別の記事でまとめています。

12. まとめ:できる人に近づく教育とは?

”仕事ができる人材を育てる”ためどうしたら良いのか?
考察してきました!
まとめると
- 新人の現在地を正確に把握する
教育者は、新人がどこにいるのか、
どの程度のスキルが身についているのかをしっかり見極め、適切なフィードバックと軌道修正を行います。 - 思考のアウトプットを支援する
新人が自分自身の考えを言語化し、先輩や上司とすり合わせることで、成長に必要な気づきを得られる環境を整えます。 - 具体的な行動指示と考え方の支援
単に「こうしなさい」と指示するのではなく、相手の状況をみて、考え方の支援をする
になります。
「仕事ができる人」って育て方イメージできましたか?
今現在同じこと私が働いている病院内で実施中です。
特に検索力、質問力の講義のあとは質問のレベルがグッとあがって
教育がしやすい!という声が聞かれています。
さらにステップアップで、それぞれの先輩が
✅️同じ内容を統一して教える。
✅️言語化の支援を統一できれば
よりよい教育ができるのでなないのかなと思います!
目指すは、
働きやすい職場づくり=良い教育環境
それぞれが「仕事ができる!」という感覚をもつことは自信になるし、
患者さんへのケアを引き継ぐ「いいバトン」が円滑に回るようになれば、
それは、働きやすさに直結します。
チーム全体で育む教育に取り組み、
離職率がをさけ、人気がでる病院へしていきたいです。
ありがとうございました!
今日も皆様お疲れさまです!
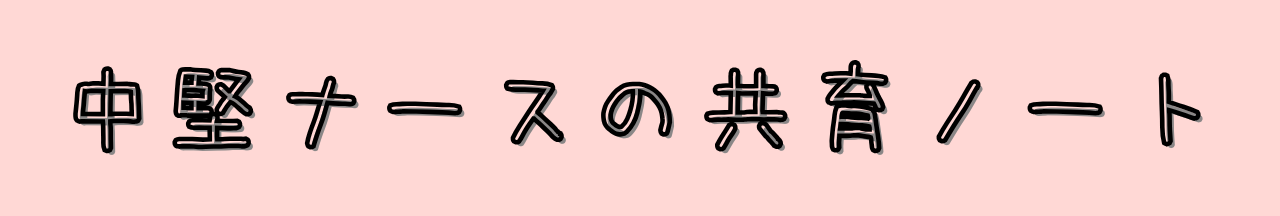

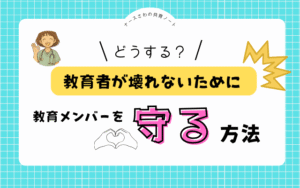
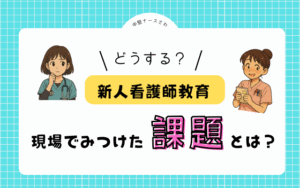

コメント